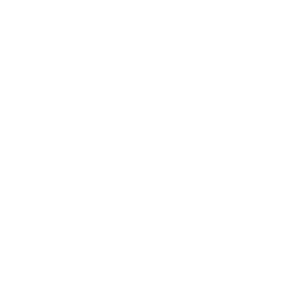さまざまな組織の創造と変革プロジェクトを手がける、デザイン・イノベーション・ファームのTakram(タクラム)で、コンテクストデザイナーを務める渡邉康太郎さん。このTALKでは、デジタル化する生活と社会への問題意識を入口に、科学と数学、資本主義と経済といった社会の構成要素の認識アップデートについて考えます。さまざまな書籍から、個と社会の未来を考える時間を一緒に過ごしていきましょう。
7回目のTALKは、「自分なりの勉強の始め方・進め方」がテーマ。日々の暮らしの中で、“勉強する”ことが、“物語”とリンクしていくのではないかという連想を深めていきながら、勉強の作法を考える、2冊の書籍を紹介してくださいました。
7回目のお品書き
■今回は“大興奮”と“連想“がいっぱい
■第6回の書籍のご紹介
・勉強=ノリが悪くなる?
・自分なりのアイロニー、か…。
・ビジネスとリベラルアーツのコネクション
・自分自身の「生」を楽しむ学びとは?
・「戦略」「インプット」「抽象化・構造化」「ストック」-4つのモジュール
・「すること」じゃない。「しないこと」を決めるんだ
・学んだことを人に話してみることの効用
・連想することがオススメ
■日本の美学者、尼ヶ崎彬(あまがさきあきら)氏の連想に興奮!
■安定した自己を捨てる=遊び
■社会で行う遊び=特別な時間=お祭り(祝祭)?
■「学ぶことを遊び、遊ぶことを学ぶ」バランス感覚
■皆さんへのコメントバック&質問への回答をします~
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
◇今回のお題(ご意見求む)◇
① あなたはどんなテーマで勉強していますか?
② あなたなりの勉強法を教えてください!
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
◎渡邉さんへのご意見、感想、ご質問をおまちしております!
ぜひ、コメント欄に投稿ください◎
ご紹介する本の要約
『勉強の哲学』(著者:千葉雅也)
https://www.flierinc.com/summary/2280
「勉強とは、獲得ではなく喪失」「自分自身を壊していく行為が勉強だ」――。現代において教養を深める大切さを説いた、良識的な千葉氏の良書がこちら。人が何かを学んでいく過程で、異なる世界・事象で引き裂かれていく、その中でどの世界にも合わなくなり、“キモくなる”ということが起こると、著者の千葉氏は言います。本書は、ノリが悪くなること、「バカ」になることを推奨しています。本書は、多くの人がなんとなく合わせてしまっている「当たり前」を疑い、言語化し、疑問を持っていくことの大切さを説く点に、面白味があります。
自分なりの「ボケ」は何なのかを考えてみたくなる1冊です。
『独学の技法』(著者:山口周)
https://www.flierinc.com/summary/1467
スキルには、時代とともに変化するものと、どんな時代になっても変わらない長期間活かせるスキルがありますが、では一体、時代に左右されないスキルとはなにを指すのでしょうか?
この疑問にヒントを与えてくれるのが、山口周氏のこちらの本だと、渡邉さんが紹介してくださいました。ここでいうスキルとは、ビジネスの領域のことだけではありません。ワインや新幹線のパンタグラフなど、自分が好きなもの、自身の知的好奇心に任せて学ぶこと=独学の技法が、本来の学びの面白さです。それが巡り巡って、ビジネスにも反映されていくのかもしれません。世の中がどれほど変化しても、独学の技法さえ身につけていれば、自分自身をアップデートしていきながら、しなやかな知性を手に入れることもできるかも……。
渡邉康太郎(わたなべ こうたろう)Takram コンテクストデザイナー / 慶應義塾大学SFC特別招聘教授 使い手が作り手に、消費者が表現者に変化することを促す「コンテクストデザイン」に取り組む。サービス企画立案、企業ブランディング、UI/UXデザイン、企業研修など幅広いプロジェクトを牽引。J-WAVEのブランディングプロジェクトで、新ステートメントの言語化とロゴデザインを行い、2020年度グッドデザイン賞を受賞。ほか、国内外で受賞や講演多数。 著書に、『コンテクストデザイン』『ストーリー・ウィーヴィング』『デザイン・イノベーションの振り子』。